
最新の知見を得るなら英語から
栄養や筋トレについて新しい情報を得ようと思ったら、英語圏から学ぶことは避けて通れません。
特に菜食/ヴィーガン/プラントベースの界隈は、日本語での情報が少ないですよね。僕がブログを書いている理由のひとつでもあります。
数年前にもトレーニングプログラムについて英語の本を買って読んだことがあるのですが、今回は栄養、特に菜食に関する本を読んでみようと思い立ちました。
かなり大変な作業でしたが、得るものは大きかったです。
FIBER FUELEDとは
今回読んだ本はこちら。ニューヨークタイムスのベストセラーを2回受賞しています。
本書のほかに、レシピブックも出ているようです。
著者は消化器専門医のWILL BULSIEWICZさん。ネット上ではDr.Bと呼ばれていることが多いですね。
プラントベース界隈、特にホールフード・プラントベース(WFPB)の情報に触れていると、そこそこ見かけます。
元は肉好き→奥さんの影響で菜食に
Dr.Bは仕事にどっぷりな医者・研究者。家にもあまり帰らず、キャリアに没頭する生活をしていたようです。
菜食に興味を持ったきっかけは奥さん。
ハンバーガー・ステーキ・ソーダなどのSAD(標準的なアメリカの食事)を食べていましたが、学会の滞在先でいまの奥さん(ヴィーガン)と出会います。関係を築いていくなかで、奥さんのほうが自分よりもたくさん食べているのに太っていないことに驚き、自分も菜食をしてみようと思い立ちました。
1日1回の菜食を取り入れてみるとすぐに体調がよくなり、ペスカタリアン→ヴィーガンへと進んでさらに菜食の健康効果を実感。研究者としても数々の論文・データを見て確信に至り、菜食の中でも腸内細菌・食物繊維の研究にのめり込むキャリアを送るように。
このように自身の実体験・医者として患者さんの治療に携わった現場経験・研究者としての科学的な視点、これらを組み合わせた本となっています。
本の構成
全体で3章、細かくは10セクションに分かれています。
PART1 知識は力なり
1.ヒトの健康の原動力は人間ではない(=腸内細菌のおかげである)
2.21世紀の生活…食べ過ぎ、栄養不足、過剰医療
3.ファイバー・ソリューション…短鎖脂肪酸とポストバイオティクスこそが絶対
PART2 ファイバーヒュールドのアプローチ
4.虹色を食べて、あなたの夢を実現しよう
5.神経質な腸といっしょに、植物への情熱を探そう
6.発酵の国、新興中
7.プレバイオティクス・プロバイオティクス・ポストバイオティクス
8.食物繊維の多い食べもの
PART3 ファイバーヒュールドの計画
9.ファイバーヒュールドは365日のライフスタイル
10.ファイバーヒュールド4週間チャレンジとレシピ
翻訳読書のやりかた
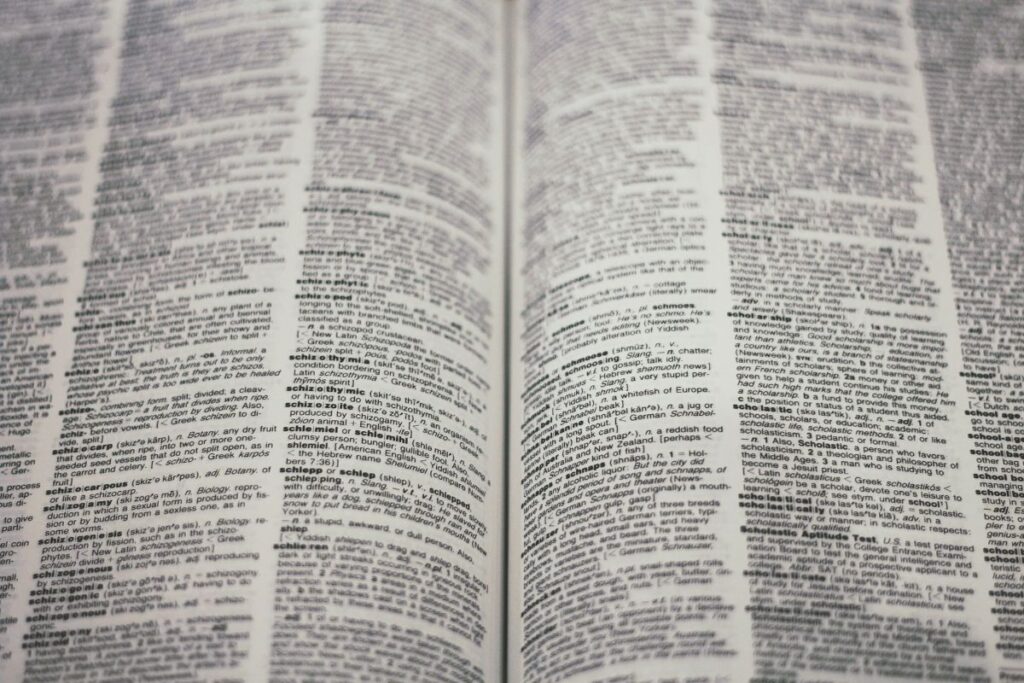
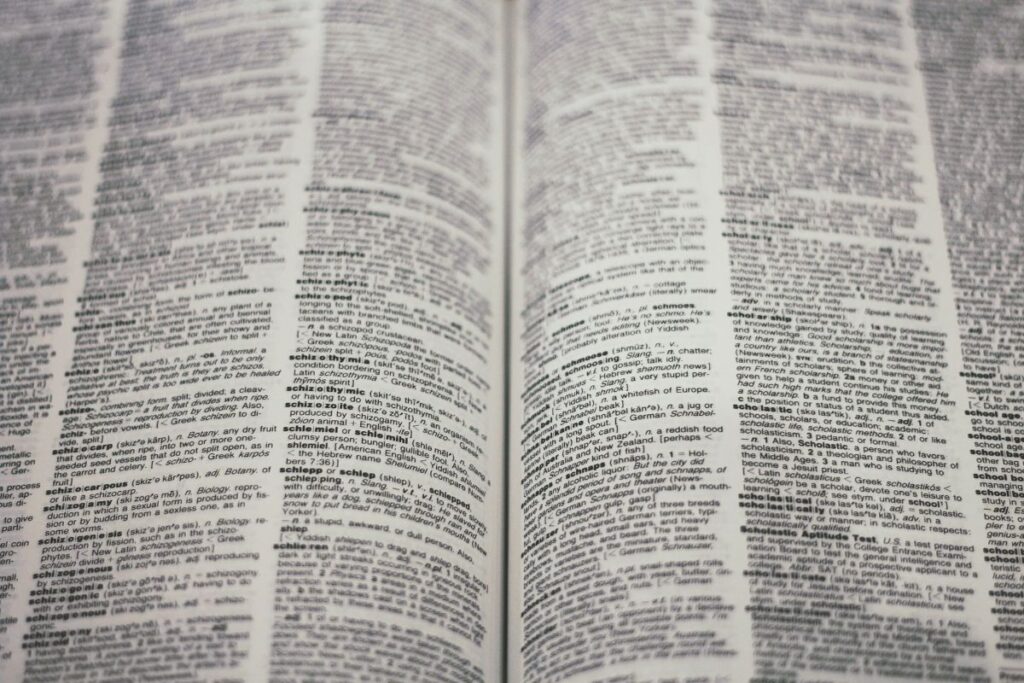
さくさく読んでいけるだけの英語力があればいいんですが、残念ながらそれほどの語学力は持ち合わせていません…。
今回は以下のような手順で翻訳し、それをGoogleドキュメントにまとめ、あとからまとめて読み返すという方法をとりました。
DeepLにはスクリーンショットの機能があるので、1ページ丸ごと読み込みます。
文章や単語の切れ目でカットして、次ページと組み合わせたりもしました。
意味がわかりにくいところや、慣用句・スラング・ニュアンスはその都度検索or辞書で対応。
1冊を通して強調されていたこと
それぞれの章で繰り返し強調されている内容もあり、特にこの3つが強調されていました。
・いろいろな植物を食べることが最優先
・腸は筋肉と同じ。トレーニングで育つ
・腸内環境が変わるまでに4週間かかる
いろいろな植物を食べることが最優先
腸内環境の健康度を測る唯一にして最大の要因は、腸内細菌の多様性だそうです。
食べものや食物繊維の種類それぞれに対応する細菌がいるので、いろんな種類の植物性食品を摂取することが大切。
具体的な数字として、1週間で30種類の植物を摂取することが推奨されていました。
食事療法に万能はない
腸内細菌叢は指紋と同じようなもので、同じ腸内フローラを持つ人はひとりとしていない。
他の人には効果があっても自分には効果がなかったりするのは、個人が持つ腸内細菌の個性によって左右されることがあるようです。
たとえば、豆類を食べてもお腹は張らないけど、たまねぎやにんにくを食べるとお腹が張る、というように、その人が持つ腸内フローラによって得意な食品と苦手な食品があります。
そのため最後の4週間チャレンジのプログラムにおいても、各FODMAPごとに代用する食材や避けた方がいい食材を細かく指定しており、さすが消化器専門医だな…と感服しました。(FODMAPについては後述します)
腸は筋肉と同じ。トレーニングが大切
食事のたびに、腸はジムに行っていると想像してください。
腕のトレーニングをしても足に筋肉はつきませんし、ジムに通い始めた初日から100kgのバーベルを持ち上げるなんて無理ですよね。
そんなイメージで、食物繊維は野菜だけでなく豆や穀物からも取り入れた方がいいし、腸に良いからといっていきなり大量に食べても、腸は処理しきれません。
いろんな筋肉をバランスよく鍛えること=いろんな植物を食べること。筋肉にたんぱく質が必要なように、腸には食物繊維が必要です。
食物繊維を食べるのに苦労する人ほど、食物繊維が必要
IBSやSIBOなどすでにお腹の不調がある人にとって、豆類や野菜など食物繊維を食べることはお腹の不快感を引き起こすトリガーになります。それなら食べないと決めちゃったほうがラクですよね。
でもずっと避け続けるだけだと、悪くなった腸内環境を整えることはできません。
ここのDr.Bの例え話がわかりやすくすごくグッときたので、少し長いですが引用します。
膝に関節炎があるからといって、電動スクーターを買って歩くのをやめますか?
歩くのをやめれば足の筋肉は減り、体重が増えて、血圧やコレステロールは高くなり、気分が落ち込みやすくなります。
でも膝だけは痛くない。こんな生活を送りたいですか?
〜中略〜
リハビリをしよう、足腰を鍛えようと決意すれば、膝の痛みが軽くなるだけでなく、体全体の健康も維持できます。
はじめは痛くて大変かもしれませんが、最初のハードルさえ乗り越えれば少しずつ改善していくんです。
腸内環境も同じです。最初の不快感を乗り越えてください。
そうすれば体重が減ったり、コレステロールが低下したり、お腹の調子だけではない健康が手に入るのです。
スロー&ロー!
食物繊維を増やすときはとにかくゆっくり、少しずつ!(slow&low)
いまの自分の腸内細菌たちは、どのくらいの量までなら耐えられるのか。FODMAPのチェックも1種類ずつ行い、お腹の調子を確かめます。
自分の腸内細菌の長所と短所がわかったら、ゆっくりと食物繊維の種類や量を増やして、腸をトレーニングしていきましょう。
腸内環境が変わるまでに4週間かかる
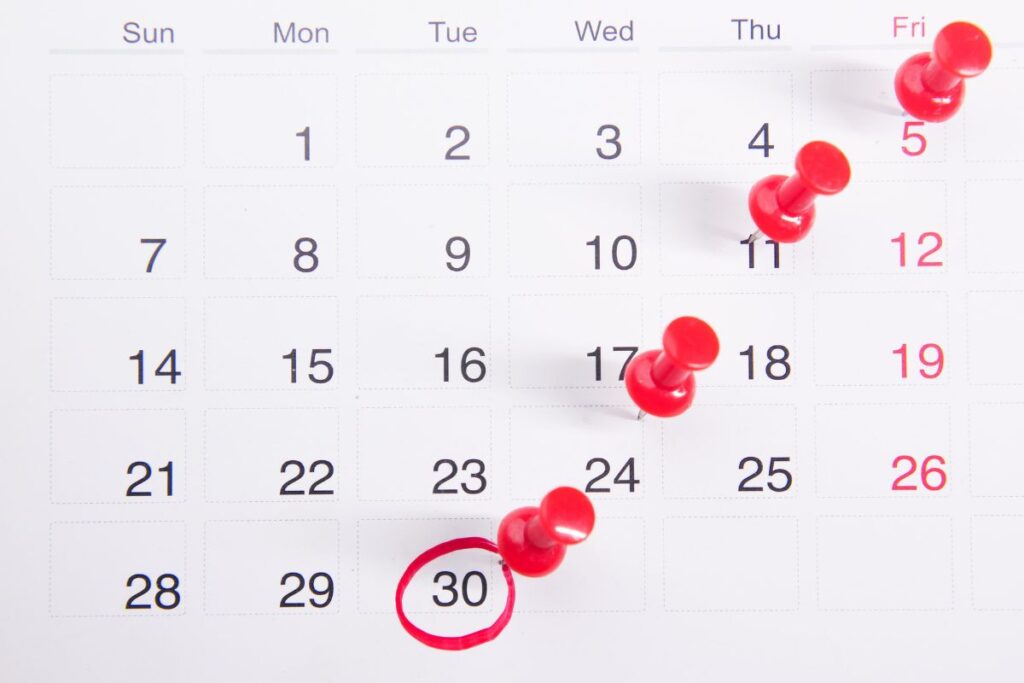
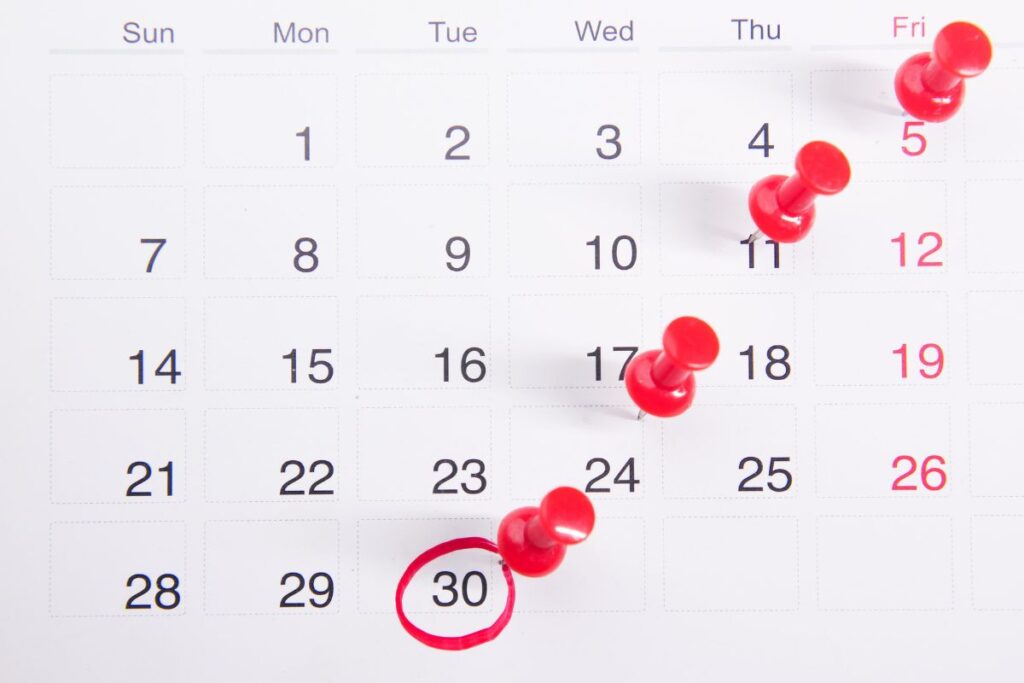
腸内環境の変化にはおよそ4週間という数字が共通するようです。
・赤身肉を食べるのをやめたあと、体内のTMAOレベルが減少するまで
・抗生物質で腸内細菌が死滅してしまった後、元の状態に回復するまで
・食物繊維を食べる量を増やしてから、それを処理できる消化酵素が作れるようになるまで
反対に抗生物質は5日間飲むだけで腸内細菌の1/3が死滅するとのこと。
抗生物質の不適切な処方・利用については近頃よく話題になっているので、その必要性については慎重に考えるべきでしょう。
抗生物質の摂取後、プロバイオティクスを摂取すべきか?
Dr.Bは推奨していません。プロバイオティクスは、かえって元の状態に戻るまでの時間を長くしてしまうようです。
そのかわりに食事に集中し、多種多様な植物性食品を食べることをすすめています。これらから得られるプレバイオティクスが腸内細菌たちの栄養となり、回復が早まるとのこと。
抗生物質投与後に限らず、腸内環境を整えるための優先順位は以下の通りです。
1.さまざまな植物を食べる
2.プレバイオティクス
3.プロバイオティクス
FODMAPとグルテンについて
食物過敏症やIBS・SIBOなどでお悩みの方は、FODMAPやグルテンについても気になっている人が多いと思います。
本書ではかなりページ数を割いて詳細に解説されていたので、お悩みの方はぜひご自身でも買って読んでみるのがおすすめです!
FODMAPとは
発酵性オリゴ糖、二糖類、単糖類、ポリオールの頭文字をとったもの。
これら4種類に共通する特徴は、発酵しやすく吸収されにくいこと。この影響で腸に水分が増えて、下痢になってしまうんです。それ以外では消化不良、お腹の張りや不快感、ガスの溜まっている感じ、なども起こり得ますね。
FODMAPの消化・処理には腸内細菌が頼りになるわけですが、過敏性腸症候群など腸内細菌叢にダメージを受けている人は、この能力が低下しています。
FODMAPの情報は日本語でも増えてきているので、気になる方は調べてみてください。
FODMAPの5分類
・乳糖
・果糖
・フルクタン(小麦や大麦、果物、にんにくやたまねぎなど)
・ガラクトオリゴ糖(豆類に多い)
・ポリオール(マンニトール、ソルビトールなどの糖アルコール。果物や野菜にも含まれる)
乳糖不耐症なんかはかなりメジャーになってきましたが、ほかにも種類があります。ここで注意してほしいのが、乳糖がダメだったら他のFODMAPもダメ…ということではありません!
腸内細菌の個性によってそれぞれ処理能力の高さは違うので、どのジャンルをどれくらいの量食べるとお腹の調子が崩れるのか?を調べることが大切です。
低FODMAP食はずっと続けるものではない
低FODMAP食とは、FODMAPが多く含まれる食材を避ける食事法のことです。
低FODMAP食は自分の腸の個性を確かめるには役立ちますが、2~6週間が限度で、長期に続けるとビタミンやミネラルが欠乏するリスクがあるとのこと。
上述の通り、腸はトレーニングできます。運動不足で体がなまっていくように、特定の食べものを避け続けることで、腸の消化吸収機能も衰えてしまいます。
自分の苦手なFODMAPを食べないように避けるのではなく、処理する能力を鍛えていくことが重要です。
食事日記をつける
FODMAPへの対応力を調べる&腸をトレーニングしていくために、食事日記をつけることが推奨されていました。
食べたものを記録するのはもちろん、その後数日間のお腹の調子も書いておきます。これを繰り返すことで、何をどれくらい食べると、お腹に問題が起こるのかを特定しやすくなりますよね。
どの食材・どのFODMAPが弱点なのかわかったら、上述のスロー&ローに則って食べる量を調整して、腸内細菌を育てていきます。
グルテンフリーって腸にいいの?
セリアック病の検査を受け、その可能性を除外できているなら、グルテンを避ける必要はありません。
グルテンフリーを提唱する人たちがよく話題にしているデータは試験管での研究とのこと。この研究ではグルテンが炎症を引き起こすかのようなデータがありましたが、実際にグルテンフリーをヒトで1ヶ月間行った研究では、善玉菌の減少・悪玉菌の増加というむしろ良くない結果が出ていました。
全粒小麦を食べることでビフィズス菌が増えたという研究も紹介されています。
本当にグルテンのせいなのか?
僕がおもしろいと思ったのが、グルテン過敏症だと感じている人に1週間シリアルバーを食べてもらった研究。
シリアルバーはプラセボ・グルテン入り・フルクタン入りの3種類が用意されました。
この結果、プラセボを食べた人よりもグルテン入りのバーを食べていた群のほうがお腹の不快感が少なかったとのこと。また、フルクタン入りのバーを食べた群はお腹の不快感が大幅に悪化しました。
これらのことから、グルテンではなくフルクタンに原因がある人もいるかもしれません。



ここから僕の私見
日本の食生活においても、グルテンは加工食品やスナック・お菓子に多く含まれています。これらを避けたほうがいいのは間違いありません。
でも、こんなお悩みをお持ちの方もいますよね。



グルテンをやめるとお腹の調子はよくなるけど、パンもパスタも食べたい!
そんな方はパスタソースやピザソース・惣菜パンなどに含まれるたまねぎやにんにく・果物のフルクタンが腸に合っていない可能性を考えるといいかもしれません。
それでもお腹の調子がよくなければ、食感をよくしてくれる乳化剤や、おいしくするための人工甘味料や糖アルコールなどほかのFODMAPの影響も警戒してみると、パンやパスタをやめずに済むかもしれませんよ!
面白かった研究・データ
ここからは気に入った内容や本書のキーワード、面白かった研究などを抜き出して紹介します。
研究成果がクリニックに導入されるまで17年かかる
新しい研究の知見が出版されてから、クリニックに導入されたり、医師の意識にのぼるまでには平均17年かかるそうです。安全性の検査とか、データの再現性などを加味すると時間はかかってしまうんでしょうが、それにしても17年は長いですよね。
そこから世間に広がるまでにはさらに時間を要するでしょうし、すでに一般化している情報が間違っていた、なんて場合には、以前のイメージを払拭するのはかなり難しいですからね。



ここから余談
たとえば、過呼吸の人に紙袋やビニール袋を渡して呼吸させる方法はすでに時代遅れで、むしろ逆効果となるケースもあるようです。僕が学生だったころにはそのように習いました(2010年代)。
これがある程度上の世代の方々になると、過呼吸=ビニール袋!というくらいに刷り込みで覚えている方もいらっしゃいます。
それ以外だと、一次救命の人口呼吸も任意性になっていますね。胸骨圧迫(心臓マッサージ)に集中する方が予後良好となる可能性を高められるようです。
「見ず知らずの他人に人口呼吸をすることをためらって、胸骨圧迫をする手が止まってしまうケースが少なくなかったこと」が理由と聞きました。
幼児のおむつから、喘息の発症率が予測できる
本書は実験や研究の話が多いのですが、中でもこれはいちばん衝撃的でした。
幼児300人のおむつを分析した研究によると、生後3ヶ月時点での腸内細菌における変化を見ることで、どの子供がその何年後に喘息を発症するかを予測できたとのこと。
さらにこのおむつについていた便をマウスに移植すると、喘息発症のリスクがあると思われる便を移植されたマウスはすべて肺の炎症を起こしたそうです(喘息と同様の症状)。



腸内細菌って肺まで影響してるの…!?
腸脳相関やセロトニンなど、脳やホルモンとの関係は広く知られるようになりましたが、まさか呼吸器までとは…。
糞便移植でBMI・体型・インスリン感受性が変化する
糞便移植つながりで他にもいくつか事例が紹介されています。
治療のための糞便移植でBMIが26→33になってしまった女性
食生活・運動量・ストレスレベルは何も変わっていないのに、体重が激増した。
一卵性双生児の研究
いっぽうは太っていていっぽうは痩せている双子からそれぞれ便を採取しマウスに移植すると、体型がその通りになった。
メタボの男性に、痩せたドナーから糞便移植を行った
インスリン感受性が改善し、血糖値が下がった。しかしこの男性は食事を変えなかったために、数週間で元に戻ってしまった。
腸内細菌叢が起こす代謝への影響
体型やインスリン感受性、血糖値まで変わるくらいですから、腸内細菌が体内の代謝に与えている影響はかなり大きいだろうと推測され、研究界は大盛り上がりとのこと。影響の範囲が膨大すぎるので、まだまだ未解明な部分も多いようですが。
食品によって血糖値の反応が大きく異なる
腸内細菌叢の個人差と関連があるようです。
将来的には腸内細菌叢のプロフィールを見ることによって、どの食品がその人の血糖値をどのくらい上昇させるか、予測できるようになるかも。
ホルモンバランスにも影響する
動物実験では、フェロモンの放出も腸内細菌がコントロールしているとのこと。
人間の実験はまだないみたいですが、恋人の匂いで落ち着いたり、逆に匂いで人を嫌いになったりしてしまうのも、腸内細菌が相性を教えてくれているのかも?
好きな食べものも腸内細菌の影響?
チョコが好きな人と無関心な人の尿を比べると、腸内細菌から発せられる代謝産物が異なっているようです。
時間をかけて一定期間同じ食事をとらせる実験でもこのような結果になっているので、同じものを食べていても人によって体の中での反応が違うということを示唆しています。
僕たちは自分が好きなものというより、腸内細菌が欲しがるものを食べさせられているのかもしれませんね。
Dr.Bおすすめの食品
それぞれの頭文字をとって、FGOALSと名付けられていました。
F…フルーツと発酵食品(fermented)
G…緑黄色野菜(グリーン)と全粒穀物(グレイン)
O…オメガ3シード
A…芳香族(アミン系の植物。たまねぎやにんにく、ニラなど)
L…豆類(legumes)
S…スルフォラファン(を含むアブラナ科の野菜)
A&SはChop&Stop
アミン系の植物が含むアリシンという成分には抗菌・抗真菌・抗ウイルス作用があるようですが、これらは酵素反応によって作られます。
アリシンを最大限活性化させるためには、刻んだ後に10分間待つのがベストとのこと。
ちなみにこれはアブラナ科の野菜(スルフォラファン)でも同じです。マイケル・グレガー先生の著書にも書かれていましたね。こちらは日本語で読めますし、菜食や健康的な食事に興味があるならどんな人が読んでも損しないと思います。
ファイバーヒュールド4週間チャレンジ
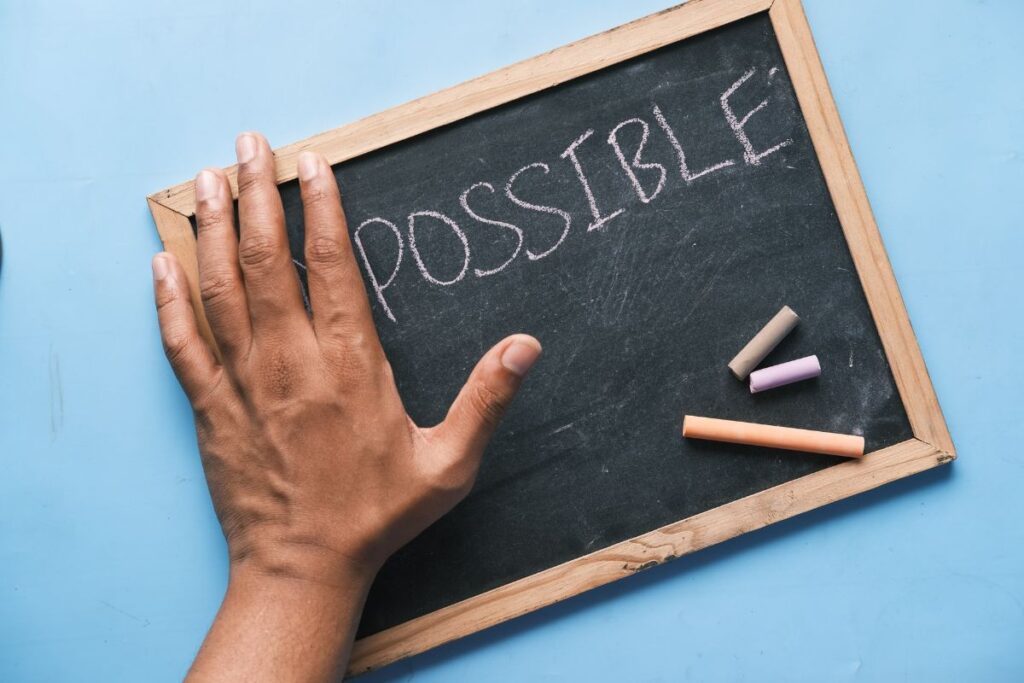
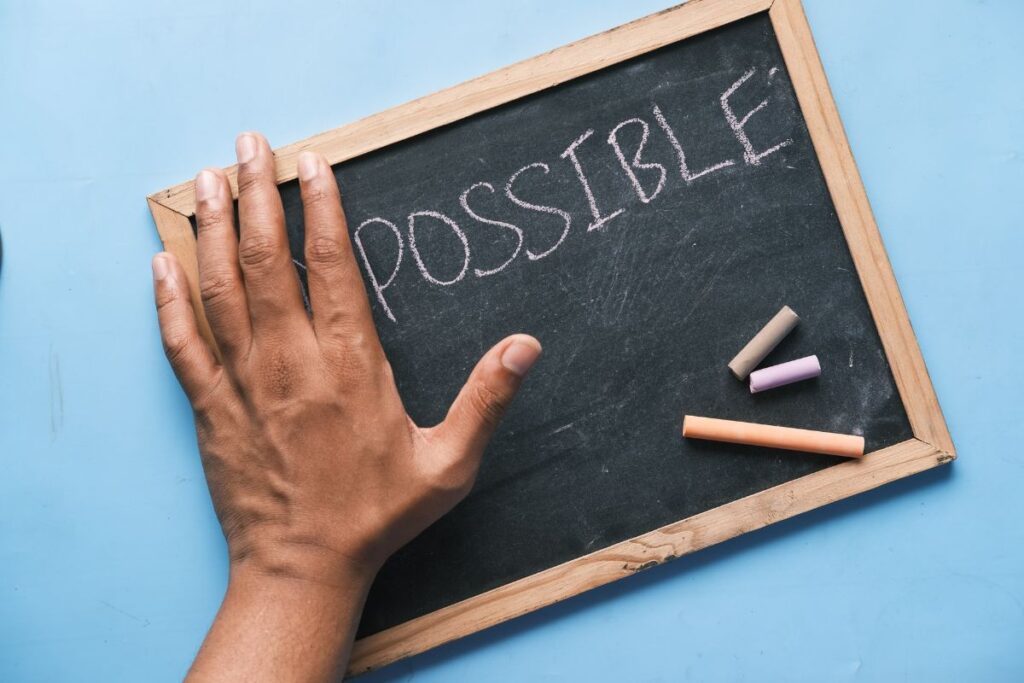
最後の章はライフスタイルを変えるためのマインドセットの解説と、4週間分(28日間の朝昼晩3食)のレシピが掲載されています。
このレシピ集がかなりのボリューム。クイックフィックス・メニューとして時短料理やつくりおきができるものも紹介されていて、かなり実用性がありそうです。
ただ個人的には、その前のマインドセットの解説に感動するセンテンスが盛りだくさんでした。
4週間という期間の理由
よくあるデトックスプログラムのように、1週間や10日間のほうがもっと取り組みやすいチャレンジにできたかもしれません。でもその程度の期間では、すぐ元の習慣に戻ってしまいます。
ファイバーヒュールド4週間チャレンジはやったら終わりではなく、これから新しいライフスタイルに切り替えていくためのスタートダッシュのようなものと考えてください。
上述した通り、腸内環境の変化にはおよそ4週間かかるという研究結果も加味しての期間なのでしょう。4週間の中では同じレシピを繰り返し作ることが何度かあるので、レシピを記憶するのにもちょうどよさそうです。
健康のためのマインドセット
・成功やスキル、完璧さを過度に評価しない。努力、学習、粘り強さを尊重する。
・失敗しても気にしない。自分のために何ができるかという挑戦と、そこから学ぶことを楽しむ。弱さや不完全さを責めるのではなく、ポジティブなところを見つけて、進歩を祝う。
・たとえば、タバコを1本吸ったくらいでは死んだりしない。でも習慣にしてしまうのは良くない。良い習慣をつくることに集中する。
ついトレーナー目線で読んでしまいましたが、頷けることばかりでした。僕の指導経験としても、気の持ちようが本当に大事だと思います。たとえば以下のような方を同じペースで指導した場合、
・毎日続けられないとストレスを感じてしまう人
・1週間に数回しかできていなくても、ポジティブに続けていける人
後者の方ほど結果が出るスピードが早いです。行動だけ見ていると、前者のほうがよさそうに見えるんですけどね。体と心のつながりは不思議です。
90%プラントベースを目指す
完璧にやろうとして、重荷に感じてしまうのはよくありません。でも目標を持つのはいいことです。
90%と余裕を持った目標にしておけば、プレッシャーを避けられます。
ほかにも、ブルーゾーン(健康長寿で有名な5つの地域)の食文化が90%以上植物性だったことが理由としてあげられていました。
ブルーゾーンの本は日本語で読めますので、興味がある人はぜひ。僕はこの本が大好きで、自分のライフスタイルも変えたほどです。沖縄も紹介されていますよ。
ちなみに、ここでいうプラントベースは未加工の植物性食品(ホールフード)のこと。プラントベースならなんでもいいわけではありません。ヴィーガンにするだけでは健康的な食事といえないので、注意してください。
グラスフェッドのお肉や乳製品はどう?
グラスフェッドのお肉はホルモンや抗生物質まみれのお肉に比べればいいかもしれないが、それは噛みタバコのほうがタバコより健康的と言っているようなもの。
自分はどうしたいのか、時間をかけてゆっくり考えてみてください。
90%を守れていれば、残りの10%はその人次第というのがDr.Bのスタンス。もちろん100%を目指せたら理想的ですが、急ぐ必要はありません。
食事と倫理観の問題についても、時間をかけて自分の立場を決めることが推奨されていました。
菜食に移行するためのステップ
動物性食品を完全に控えたい人向けに、以下の順番がおすすめされていました。
牛肉→豚肉→鶏肉→卵→魚の順番で取り除き、豆腐と豆類に移行する。
豆類から充分なたんぱく質を摂れるようになるのが理想ですが、豆類をたくさん食べるためには腸内細菌の適応が必要です。
こんな感じで徐々にお肉やお魚を減らしていく、というのは本書以外でもよく勧められていますね。僕個人としても、こういう方法ならどんな人でも取り組みやすいと思います。
僕も菜食でSIBOから回復しました
以上、FIBERFUELEDの感想&要約でした。
一大プロジェクトが終わったかのような気分です。やっぱり英語読書って大変…。ですが、翻訳を終えて丸ごと読み直せる状態になったときは本当にワクワクしました。知的好奇心っていいものですね。
実は僕も、菜食をはじめたおかげで過敏性腸症候群とSIBOを克服できたんです。菜食に救われた恩返しなんて言うとおこがましいですが、これからも勉強&情報のシェアをできる限り続けていきたい、改めてそんな気持ちになれる経験ができました。
そもそも、日本では出版されていない本でも電子書籍なら読めるという時代の変化に感謝しないといけませんね。
この記事はあくまで僕の備忘録のようなまとめですので、ぜひ原著も読んでみてください。苦労して読むだけの価値があるはずです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
筆者はXもやっています。ブログの更新情報や最新の栄養学・菜食のレシピを投稿していますので、よかったらフォローしてください◎
あなたの周りにこんな方はいらっしゃいませんか?
このブログは、現役のパーソナルトレーナーであるまーしー(@marcyplantbased)が書いています。
あなたの周りにこんなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
・そろそろ健康を大切にした暮らしがしたい
・運動不足だけど、ひとりでは運動が続けられない
・菜食を始めてみたいけど、栄養バランスが気になる
そんな方のために、パーソナルトレーニングやオンラインカウンセリングを受付中です。
気になった方は以下のボタンからお気軽にご相談ください◎











