
食物繊維って2種類あるんだ。バランスとか気にした方がいいのかな?



水溶性は意識して取るのがよさそうだよ
理想の割合にエビデンスはあるのか?
食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があり、それぞれはたらきが違います。
そこで気になるのがバランス。どちらか片方が多いほうがいいのか、それともバランスよくとったほうがいいのか?検索してみると、水溶性:不溶性=1:2と書かれているページをよく見かけます。
しかし根拠を示しているものが見つからなかったので、いろいろな研究を調べてみることにしました。
理想の割合にエビデンスはあるのか


食物繊維をおおまかに分けると、水溶性食物繊維・不溶性食物繊維の2種類。体内でのはたらきがかなり違うので、区別して覚えたほうがいいと思います。
さて、はたらきが違うとなればバランスよく食べたほうがよさそうです。PFCバランスなどもある程度のパーセンテージが決まっていますしね。
しかし腸内環境や食物繊維については、はっきりしていないことも多いのが現状。
最近は注目度が高まって研究もさかんに行われているようですが、まだまだ発展途上なので、エビデンス(科学的根拠)が確立しているものは多くありません。
水溶性:不溶性=1:2が理想?
Google検索で「食物繊維 バランス」のように検索すると、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の理想の割合は1:2と記載されているページを多く見かけました。



まあそんなもんだろうね〜
と納得はできるのですが、ちょっと疑問に感じるところも…



こんだけいろんな記事があるのに、どこにも根拠の紹介がない
はたしてこの1:2という数字はどこから出てきたんでしょうか?
pubmedを調べてみる
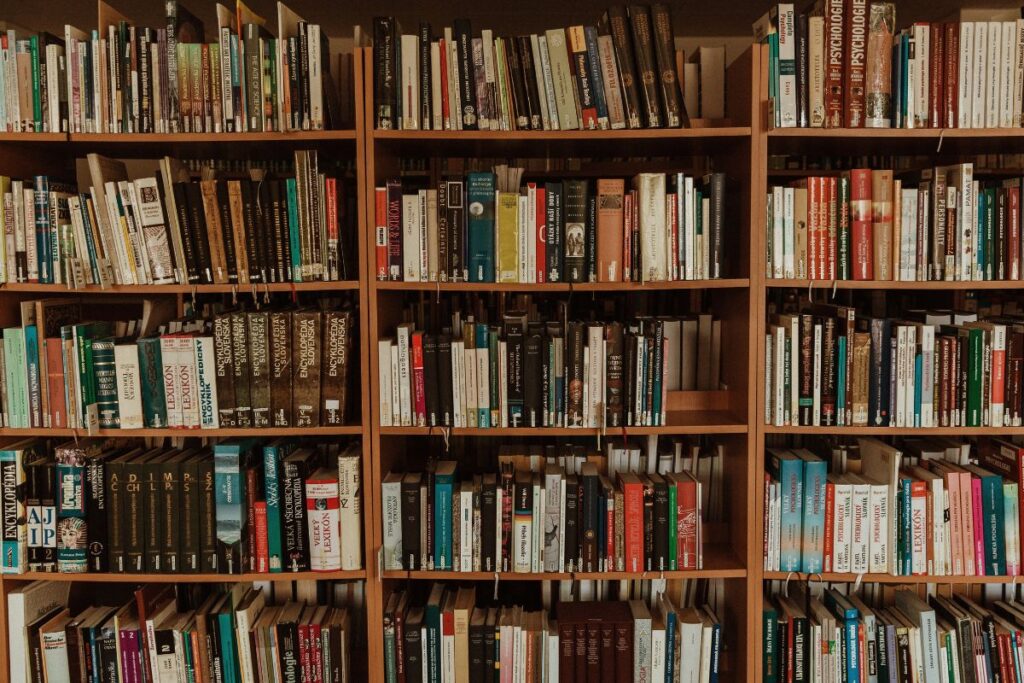
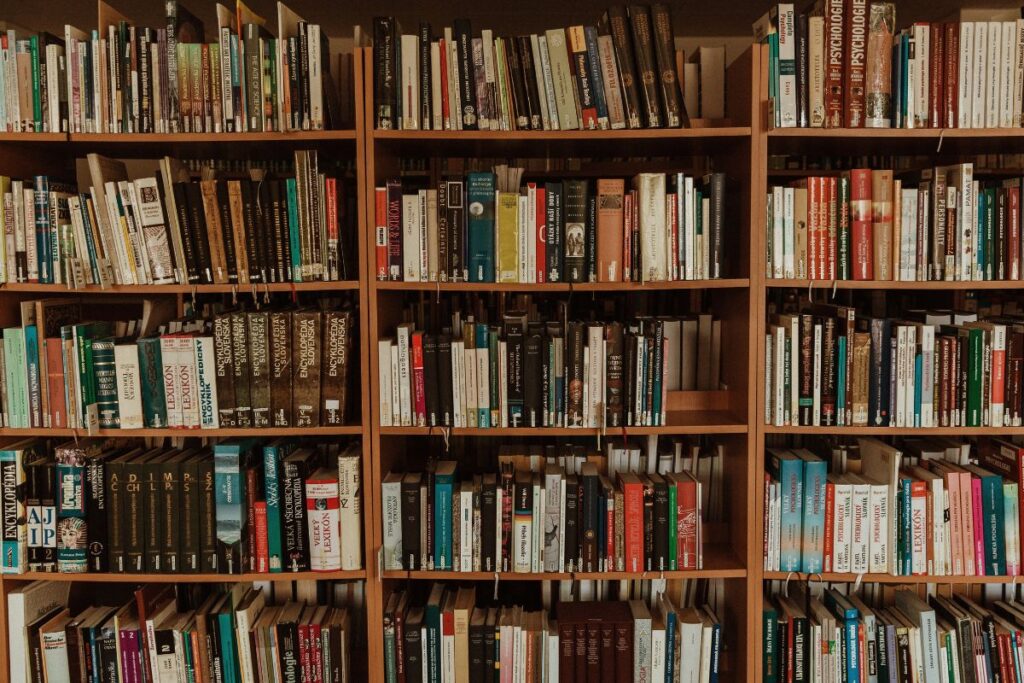
インターネットに古くから伝わる「ソースは?」というあいことばに従い、食物繊維の割合を調べた研究がないか、ざっと調べてみました。
ソース=source 情報源、情報元のこと。
ある程度エビデンスレベルの高いものを調べたいと思いましたが、研究の条件や内容まで細かくみていくのは大変です。
そこで今回は、メタ分析とランダム化対照試験に絞って検索しました。(これでも大変でしたが…)
fiberの研究をピックアップ
以下の3つでそれぞれ検索。
・dietary fiber(食物繊維)
・soluble fiber(可溶性・水溶性食物繊維)
・insoluble fiber(不溶性食物繊維)
Abstractを中心に読み進め、本文が読めるものはそれも読みました。気になったものを5つほど紹介します。
①水溶性食物繊維が体重に与える影響
・水溶性食物繊維は平均体重を減少させる。糖尿病やメタボの場合、より大きく体重を減少させた。
・エビデンスの強さは体重については中、腹囲と体脂肪については高、BMIについては低。
・前向きコホート研究では穀物繊維と体重の間に強い関連性がある。
②オーツ麦が食欲ホルモンと体重管理に及ぼす影響
・オーツ麦はBMIやウエスト、コレステロール、体重、食欲、血圧などのデータにプラスの効果があることが証明されている
・特にベータグルカンはコレステロールの低下や体の免疫サポートのために重要
・短鎖脂肪酸の産生を促進し、腸内細菌叢を改善する
・オーツ麦に含まれるポリフェノールとアベナントラミドには、抗酸化作用と抗炎症作用がある
・水溶性食物繊維、特にベータグルカンの影響が強そう
③糖尿病の管理に粘性繊維のサプリメントは役立つか?
・粘性の繊維(ベータグルカン、サイリウムハスクなど)はHbA1cを低下させる
・水溶性の繊維には血糖コントロール、脂質レベル、血圧、そして場合によっては体重を改善するなど代謝にさまざまな効果がある
・不溶性の食物繊維は結腸の健康や便のかさを増やすのに役立つ
④食物繊維を増やすことで、ミネラルの吸収率に差は出るのか
・中繊維食(水溶性8g、不溶性16g)と高繊維食(水溶性、不溶性ともに25g)で比較
・高繊維食の場合、腸からのカルシウム吸収率がわずかに低く、血中のカルシウム濃度もわずかではあるが有意に低かった
・マグネシウムには特に影響がなかった



研究で2:1が使われてる!!
⑤難消化性炭水化物の重要性
・高繊維食と低繊維食を比較する実験で、可溶性繊維は40%で設定されている
・小麦ふすまやペクチン、イヌリンなど食物繊維によって起こる効果はわずかに違う
・発酵性の繊維はミネラルの吸収を高める可能性がある
・ビフィズス菌の増加→葉酸産生の増加→閉経後の女性の骨密度、骨ミネラル量の増加に関連
・そのほか鉄分、マグネシウム、カルシウムの吸収促進効果もありそう
・逆にふすまやオオバコなどの非発酵性の繊維は吸収促進には効果がなく、むしろマイナスかもしれない→健康な男性のカルシウム吸収効率が低下した(フィチン酸の影響も考えられる)



可溶性40%だと、割合は1:1.5
全粒穀物の割合が根拠?


④や⑤の研究以外では、水溶性の繊維と不溶性の繊維の割合についての言及は見つけられませんでした。
探しかたが悪かった可能性もありますが、それにしても数が少ないので、まだ理想的なバランスとして決定的なものではないんだと思います。
それなのに、なぜ水溶性:不溶性=1:2という数字が出てきたのか。



良い報告の多い食品を参考にしたのかも?
たとえば、多くの研究で使われているオーツ麦の食物繊維の割合は1:1.9とかなり近い割合になっています。
大麦(押し麦・もち麦)もベータグルカンが多いことで有名。割合は水溶性食物繊維のほうが多いです。不溶性が多い食べ物がほとんどなので、大麦はすごい個性を持ってますね。
りんごにはペクチンという水溶性食物繊維が多く含まれています。繊維の割合は1:2.8。
1:2よりはオーバーしていますが、果物の繊維による健康効果も報告がたくさんあります。2~3くらいの範囲にちょうどいいポイントがあるのかもしれません。
| 食品 | 水溶性 | 不溶性 | 割合 |
|---|---|---|---|
| オートミール | 3.2 | 6.2 | 1:1.9 |
| 押し麦 | 4.3 | 3.6 | 1:0.8 |
| りんご | 0.5 | 1.4 | 1:2.8 |
最近の調査では、日本人は食物繊維の摂取量が5gほど足りておらず、水溶性:不溶性=1:4くらいのバランスで摂取しているようです。
理想的なバランスの根拠となるものは見つかりませんでしたが、水溶性食物繊維の量を意識して増やすことの重要性は変わらないでしょう。
というのも、食物繊維といわれてよくイメージする食べ物は大体が不溶性食物繊維だからです。野菜やきのこはほとんどが不溶性。
水溶性食物繊維が多いのは海藻や果物など。選択肢が限られていますし、野菜と比べるとどうしても食べる量は少なくなるはず。
その点、オートミールや押し麦・もち麦は主食にできるので、おのずと量も多くなります。食物繊維を増やしたいときにも、バランスを整えたい時にも役立つ万能食材です。


まとめ
以上、食物繊維のバランスについて調べてみました。
・水溶性と不溶性の理想のバランスは見つからなかった
・オーツ麦や大麦のベータグルカンがよさそう
・食物繊維を意識してとることは大事、特に水溶性
理想のバランスが1:2とする根拠は見つけられませんでしたが、食物繊維についていろいろと知ることができておもしろかったです。
論文を探して読みまくるのは大変でしたが、いい勉強になりました。また違うトピックでもやってみたいですね。
僕はオートミールを毎日食べるようにしているのですが、今回の調査で惚れ直しました。食物繊維が多すぎることのデメリットも今のところは多くなさそうでひと安心。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
栄養バランス、トレーナーに相談してみませんか?
さまざまな知識を自分で調べて、暮らしに取り入れていくのは難しいですよね。



栄養バランスが心配…
お悩みの方は、まーしーが行っているパーソナル栄養アドバイスをご利用ください。
1回だけでも受けられる栄養相談サービスなので、1ヶ月など期間の縛りはなく、毎日写真を送るような手間もかかりません。
プラントベース/ヴィーガンの食事で栄養バランスを整えるコツをお伝えし、あなたが自分の体質や目的に合わせた食生活ができるようサポートします。
参考文献
Craig WJ, Mangels AR; American Dietetic Association. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. J Am Diet Assoc. 2009 Jul;109(7):1266-82. doi: 10.1016/j.jada.2009.05.027. PMID: 19562864.
Jovanovski E, Mazhar N, Komishon A, Khayyat R, Li D, Blanco Mejia S, Khan T, L Jenkins A, Smircic-Duvnjak L, L Sievenpiper J, Vuksan V. Can dietary viscous fiber affect body weight independently of an energy-restrictive diet? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2020 Feb 1;111(2):471-485. doi: 10.1093/ajcn/nqz292. PMID: 31897475.
Shehzad A, Rabail R, Munir S, Jan H, Fernández-Lázaro D, Aadil RM. Impact of Oats on Appetite Hormones and Body Weight Management: A Review. Curr Nutr Rep. 2023 Mar;12(1):66-82. doi: 10.1007/s13668-023-00454-3. Epub 2023 Feb 15. PMID: 36790719; PMCID: PMC9930024.
Jovanovski E, Khayyat R, Zurbau A, Komishon A, Mazhar N, Sievenpiper JL, Blanco Mejia S, Ho HVT, Li D, Jenkins AL, Duvnjak L, Vuksan V. Should Viscous Fiber Supplements Be Considered in Diabetes Control? Results From a Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Diabetes Care. 2019 May;42(5):755-766. doi: 10.2337/dc18-1126. Epub 2019 Jan 7. Erratum in: Diabetes Care. 2019 Aug;42(8):1604. PMID: 30617143.
Shah M, Chandalia M, Adams-Huet B, Brinkley LJ, Sakhaee K, Grundy SM, Garg A. Effect of a high-fiber diet compared with a moderate-fiber diet on calcium and other mineral balances in subjects with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2009 Jun;32(6):990-5. doi: 10.2337/dc09-0126. Epub 2009 Mar 11. PMID: 19279300; PMCID: PMC2681046.
Alexander C, Swanson KS, Fahey GC, Garleb KA. Perspective: Physiologic Importance of Short-Chain Fatty Acids from Nondigestible Carbohydrate Fermentation. Adv Nutr. 2019 Jul 1;10(4):576-589. doi: 10.1093/advances/nmz004. PMID: 31305907; PMCID: PMC6628845.
本文中では紹介できなかったけど、面白かった研究
食物繊維は血圧を下げる
・体重の変化とは関係なく、食物繊維は血圧を下げる効果を持つ可能性がある
Rössner S, Andersson IL, Ryttig K. Effects of a dietary fibre supplement to a weight reduction programme on blood pressure. A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Acta Med Scand. 1988;223(4):353-7. doi: 10.1111/j.0954-6820.1988.tb15884.x. PMID: 2835892.
オーツ麦のベータグルカンはコレステロールを下げるが、有意差はない
・4gのオーツ麦ベータグルカンを含むスープを5週間摂取すると、コレステロールが少し下がった
・しかし有意な差はなかった
Biörklund M, Holm J, Onning G. Serum lipids and postprandial glucose and insulin levels in hyperlipidemic subjects after consumption of an oat beta-glucan-containing ready meal. Ann Nutr Metab. 2008;52(2):83-90. doi: 10.1159/000121281. Epub 2008 Mar 11. PMID: 18334815.
水溶性食物繊維は過敏性腸症候群(IBS)の症状を緩和する
・水溶性食物繊維は過敏性腸症候群(IBS)の症状を緩和する
・不溶性食物繊維ではこの効果がみられない
Nagarajan N, Morden A, Bischof D, King EA, Kosztowski M, Wick EC, Stein EM. The role of fiber supplementation in the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2015 Sep;27(9):1002-10. doi: 10.1097/MEG.0000000000000425. PMID: 26148247.
食物繊維は脳卒中のリスクを下げる
・水溶性食物繊維・不溶性食物繊維の両方が脳卒中リスクを下げる
・穀物繊維の場合は有意な差ではなかった
Li DB, Hao QQ, Hu HL. The relationship between dietary fibre and stroke: A meta-analysis. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2023 Aug;32(8):107144. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2023.107144. Epub 2023 May 15. PMID: 37196565.



